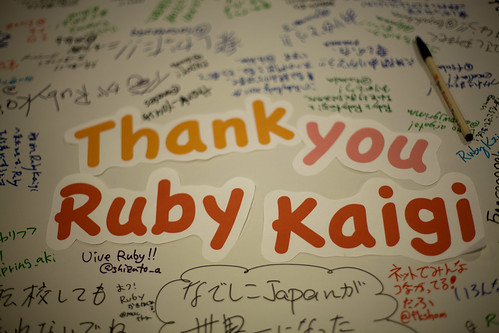移行します
ダイアリーは本格的に未来が見えないっぽいので http://kei-s.hatenablog.com/ に移行します。ほんとはほかのブログシステム使ってみたいけどいいや。
ご連絡
2011/09/15 付で現在のお勤め先を退職することになりました。おつかれさまでした。ありがとうございました。
2011/09/09 が最終出社日なので、ここを利用してご連絡ということにさせてもらいます。
振り返ると、本当に無茶苦茶いろんなことを学ぶことができました。働くということ。成果を出すということ。プログラミングをするということ。「ものづくり」をするということ。チームを育てる、チームで立ち向かうということ。サービスを立ち上げ、続けるということ。
RubyKaigi へのスタッフ参加など社外の活動にも理解をしてくれて、本当に本当に、いろんな機会を得て、いろんな経験をさせてもらいました。
就職する前から関わらせてもらっていた会社なので離れるのはそれなりに感慨深いです。いまの会社が進むべき方向と、自分が自分の成長のために進みたい方向を吟味して、決定をしました。
"Love it or Leave it" は二者択一じゃないだろうし、これが今生の別れなはずもなし。応援しています。がんばります。
さて、
次、というはなし。少なくともひと月ふた月くらいは「どこにも属さない」というのをやってみようかなと思ってます。いわゆるフリーランスという形なんでしょうか。どこにも属さないのをいいことに、いろんなものを見たい知りたいという感じです*1。
「ちょっと話きいて」「話きかせて」「説教させろ」等々ありましたら、ぜひお声がけください!
まとめ
がんばります。ひきつづき、よろしくお願いします。
*1:今月末は RubyConf にも行くし
ここに書かれる内容はすべて私事です
そういえば、社会人になってましたとかさえここに書いてなかった気がする。懸命に働いてました!(過去形)
WEB+DB PRESS で Ruby の連載をしています。
いま出ている最新のは Vol.64 ですが、前号の Vol.63 から「Rubyわくわくナビ」という連載を @june29 と担当させてもらっています。
Vol.64 ではじめて自分の記事が出たのでご紹介宣伝エントリ。

- 作者: 柏木泰幸,松野紘明,林聖高,杉義宏,飯塚直,高橋征義,徳永拓之,Tehu(張惺),中島聡,おにたま
- 出版社/メーカー: 技術評論社
- 発売日: 2011/08/24
- メディア: 大型本
- 購入: 17人 クリック: 714回
- この商品を含むブログ (16件) を見る
june29 の連載一回目のエントリはここ。
WEB+DB PRESSにてRubyの連載がはじまりました - #june29jp
Vol.64 のご紹介
「Railsでサクサク作るTwitter/Facebookアプリケーション」と題して、Twitter/Facebook 連携アプリを Ruby on Rails で作る、というのを書きました。"rails new app" から始まり、OmniAuth 経由で OAuth 認証をし、取得した OAuth で投稿するまでを解説しました。
「OAuth は知ってるけど、実際なににどうやって使うの?」という疑問や「Rails で Twitter 連携するなら OmniAuth がいいらしいけど、調べる手間がなぁ」という方に、まるっとさくっと理解できるサンプルアプリとして読んでもらえると嬉しいです。
良い道具を知ることで発想が広がり、新しいモノがどんどん出てくる一助になれば嬉しいです。
今回の記事で作ったアプリはソースコードを公開しています。参考にしてみてください。
GitHub - wdpress11rb/intr: WEB+DB PRESS Vol.64「Rubyわくわくナビ 第2回」
記事のレビューを @hsbt さんにお願いしました。ありがとうございました!実際にアプリを動かすときにハマリそうなところ、セキュリティで気をつけたほうがよいところなどを指摘してもらい、見落としていたところを的確に拾っていただきました。
タイトル裏話
自分たちで出したタイトル案はまるっとお蔵入りしたのでひとつご紹介。
いちばん最初に出てきた案は "Ruby.enjoy!" でした。短かすぎたのが敗因かなー。
September
夏が過ぎ去る。
RubyKaigi2011でした
ここで得たなにか文章を残すことはとても大事に思うんだけど、文章にするのがとっても大変です。
あと、これはわたしのブログなのでですます調とかぐちゃぐちゃだよ。
わたしと RubyKaigi (事実ベースのこと)
RubyKaigi2008
(これ以前はRubyKaigiに関わりがなかった。Ruby札幌のひとたちからお話を聞いたくらい)
- RubyKaigi2008(つくば) に、上京して行きやすくなったので参加した。札幌でお世話になった方と再会できた。(谷口先生の結婚お祝い寄せ書きを書いた覚えがある)
RubyKaigi2009
- RubyKaigi2009(東京) の2ヶ月前くらいにしまださんから、gihyo.jp での当日レポート係を june29 と担当しないか、というお誘いが来た。
- レポート班として RubyKaigi2009 の直前レポート、当日レポート3日間、開催後の運営委員長のかくたにさん (と偶然居合わせた実行委員のしまださん) インタビューを記事にした。
- ふりかえると、インタビューに同席できたのは、RubyKaigi とそれを通して Ruby に関わるうえで大きなキッカケだった気がする。
RubyKaigi2010
- TokyoRubyKaigi03 のときに、しだらさんとかくたにさんから、RubyKaigi2010 でコミュニケーションデザインを実行委員としてやらないか、というお誘いが来た。
- 2009 のレポート班の体制では 2010 は乗り切れないとおもって、takkanm さん、sugamasao さん、ukstudio さんを仲間に誘った。
- コミュニケーションデザイン班というのを june29 と組織した。
- サブスクリーン用に Web アプリを作って、Chrome で全画面表示したらいけるんじゃない?というのを作った。norio さんのデザイナーズコミットでぐんとよくなったのがうれしかった。
- 会場が広かったのでやりたいことをいろいろやった。書道とか。
- 撤収のことを考えてなくてドタバタになっちゃった。
RubyKaigi2011
- 「2011 は最後の RubyKaigi」というのを初めて聴いたのはいつだったかなぁ。2010 のための KaigiKaigi を開いていたときだったような。
- たしか RubyKaigi2010 最終日のスタッフ打ち上げのあと、帰りのつくばエクスプレスの中でかくたにさんから「(スタッフは)来年どうする?」って言われた気がする。やりたいです、と即答した気がする。
- レポート班は t, s, u の三人にお任せすることにした。さらに oshow さん、hokkai7go くんが参加してくれた。自分たちが名前をつけて作ったものをさらに良いものにつなぐことができたのは、とても良い体験だった。
- さらにコミュニケーションデザイン班としてコミットをした。
- 2010 のサブスクリーンがすでに「ふつう」になってて (tenderlove キーノートのサプライズのときも、事前に「翻訳やめてっていうからやめてね!」と言われてて、「翻訳サブスクリーンある前提で話が進んでる...!」とおもった) うれしかった。
- 2011 では、Twitter ログをどっさり記録したり、システム全体を Rails で書いたりした。当日 JS 周りでバグっぽい挙動に遭遇したりしたけど、2日目にはどうにかパッチをあてた (翻訳サブスクリーンが白い画面になってたのを見たとしたら、それは裏でバグ取りをしていた証)
- 会場は昨年より自由に使える場所が少なかった。けれど、昨年の経験から、「事前に決めすぎない。現場で作ったほうがよいものになる」というのの見極めが出来た気がする。
- 現場でかくたにさんと会場設計をしたときの「こっちから人が流れるから、(身振りで)こういう流れをつくる。そうすると机はここに来る」というのを見ていて、設計力を感じた。
- 今年はコミュニケーションデザインからもう少し手を伸ばして、物品まわりの手配もはがすことができた。
- トランシーバ、喫茶飲み物、会場物品、文房具小物など、まるっと情報を集約できたのはある程度良かった気がする。
- 2010 での懸念だった、撤収もうまいことこなせた。撤収前にウォークスルーができたのがよかった。計画重要でした。
わたしと RubyKaigi (スタッフのこと。あるいは感謝について)
実行委員、当日スタッフのかたがた
RubyKaigi 最終日の撤収のあと、高橋会長の最後の挨拶のあと、かくたにさんの「解散!」という声で、3日間と数ヶ月のチームは解散したのでした。
某 Anonymous Diary の方と同様に「あまりにも個人的なメッセージ」になってしまうので、それぞれお会いしたときにお話ししたいです。
ちょっとだけ名指しさせてください。
- 現場棟梁のかたがた
- 「現場棟梁」という名前が実にしっくりくる、現場を支える屋台骨のみなさまでした。現場棟梁分科会を繰り返し開けたのが、今回勝つるに至ったポイントだったかなと振り返っています。ありがとうございました。
- たなべさん、あづみさん
- 今回、物品まわりや会場の撤収作業で、ほんとうにたくさん助けられました。おふたりがいなかったら自分はめちゃくちゃテンパってたとおもいます。ありがとうございました。
- KaigiFreaks レポート班のみんな t, s, u, o, h
- おつかれさまでした。ここのみんなは年齢も近いので、単純に友達なんですよね。それがうれしいです。
- ZoAmichi くん
- いきなり名指しするけど、フロアマップに手を挙げてくれたのは本当に嬉しかったのですよ。ありがとう。
- しだらさん
- ほんとうにいろいろな場面でお世話になりました。今年はある程度うまくやれたんじゃないかとおもっています。ありがとうございました。
- 高橋会長、かくたにさん、しまださん、ささださん
- ほんとうに、おつかれさまでした。ありがとうございました。
参加者のかたがた
今回、何人かのかたに「ぜひ RubyKaigi 来てみてください!」と無茶な誘い方をしていたのだけど、無茶を承知で誘いたいくらい RubyKaigi に参加することに良さがあると思えていました。そんなお誘いに乗っていただいて参加してくれて、なにかを得られたのならとてもうれしいです。
会場でお会いできたみなさん、忙しそうにしちゃっててごめんなさい。もう少し余裕をもてればよかったです。
参加したみなさん(あなたですよ)、ありがとうございました。
わたしと RubyKaigi (スピリチュアルな感じのこと)
Kaigi
RubyKaigi に contribute したことで、「Kaigi 的ななにか」が潜んでいることに気づいたんです。文化祭的なノリが合う人合わない人いるだろうけど、なんでああなるかというと、事前に作っている人たちも楽しくなっちゃうからだと思う。「今回、夜の部も借りれることになったけどどうしようね?」「"夜のRubyKaigi"やる?」「"闇"にしようぜ!厨二っぽい!」みたいな、大人げない大人が全力で楽しむとああなる、っていう。楽しんでもらうのが楽しいから、世界地図とか寄せ書きとか全力でつくっちゃうし、当日レポートだけじゃなくて事前レポートやしおりとかまで準備しちゃう。
文化祭的なノリが内輪ノリなんて言われちゃうのかもしれないけど、「みなさんにキチンと楽しんでほしい。それが楽しい。そう思いませんか?」という思いのコミュニケーションの齟齬なのかなとおもう (コミュニケーションは伝送路と伝送路の両端の問題です)。
「楽しいのも楽じゃない」のがちょっとむずかしいところなのですが。現実は目の前にある。
Ruby
2011 では例年に比べて「楽しいRuby」への参照が多かった気がする。まつもとさんのキーノートの大人げなさも、実に楽しそうだった。
とはいえ、自分自身は Ruby への contribute はしていない(し、言語よりもサービス寄りのレイヤーに興味がある)。でも、Ruby という道具はよく手に馴染んだし、Ruby のおかげで様々なものや文化を知る手がかりをもらった。Ruby を手にしたとき、モノリスに触れていたのかもしれないなあ。
RubyKaigi
Ruby と Kaigi を分けたのは、たださんの日記にもあったように、今年の RubyKaigi に参加していた人の間口がどーんと大きくなって「プログラミング言語 Ruby」とちょっとずつ離れ始めているのかもと感じたから。「プログラミング言語 Ruby」の根幹の話は正直いって難しいです(そんななかで ennnnd はすごいとおもう)。
そう感じたんだけど、会期が終わって整理していくと、RubyKaigi はやっぱり(あたりまえだけど) Ruby のことを Kaigi する場所なんだなぁとおもった。「Ruby って楽しい。そう思いませんか?」という問いかけを発していたんだろうなあと、勝手なことを言っておわりにします。